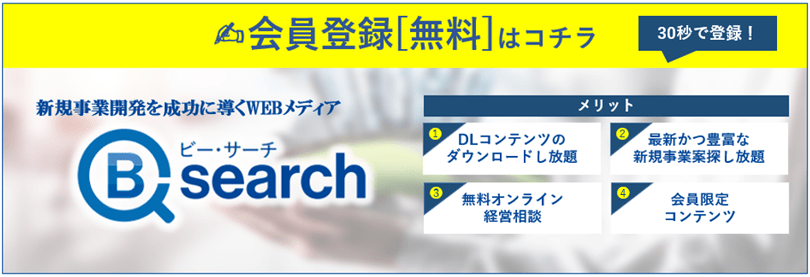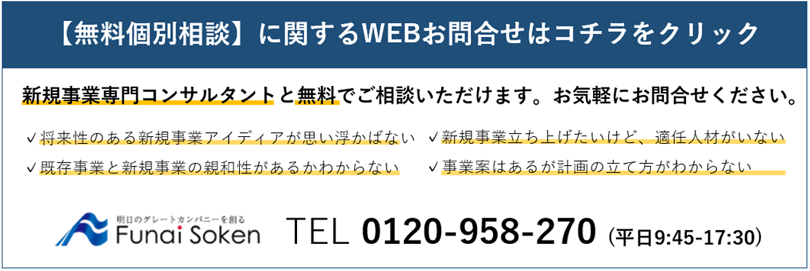「新たな事業の柱を創出せよ」
「イノベーションで市場をリードするんだ」
経営層からの期待を背負い、新規事業の担当者や責任者に任命されたものの、何から手をつければ良いのか、暗中模索の状態になっていないでしょうか。社内に経験者やノウハウが不足し、アイデアはあっても事業化への道筋が見えない。外部のコンサルティング会社に相談してみたものの、提示された高額な見積もりに「本当に投資対効果に見合うのか…」と、一歩を踏み出せずにいる。
もし、あなたがこのような課題や不安を感じているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。
この記事では、単なるコンサルティングとは一線を画す「伴走支援」というアプローチについて、その本質から具体的な活用法、そして最も重要な「失敗しないパートナーの選び方」までを徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは以下の点を深く理解できます。
●新規事業がなぜ難しいのか、その構造的な課題がわかる
●「伴走支援」がなぜ今、多くの企業で求められているのかがわかる
●自社の状況に合わせて、どのような支援を、どのタイミングで活用すべきかがわかる
●高額な投資で失敗しない、信頼できるパートナーを見極める具体的なポイントがわかる
机上の空論ではない、現場で求められる実践的な情報だけを詰め込みました。貴社の新規事業プロジェクトを成功へと導く、確かな一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひ最後までお付き合いください。
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
Table of Contents
1. そもそも、なぜ新規事業はこれほどまでに難しいのか?

多くの企業が成長戦略の中心に新規事業開発を据えていますが、その成功率は決して高くないのが現実です。まずは、その厳しさを客観的な視点から見ていきましょう。
データで見る新規事業の厳しい現実
日本の新規事業の成功率に関する統一された公的データは多くありません。しかし、様々な調査からその難易度の高さがうかがえます。例えば、スタートアップの生存率に関するデータは一つの参考になります。中小企業庁の「2017年版中小企業白書」によると、起業後に5年存続する企業は約80%ですが、これはあくまで事業継続のデータです。「新規事業が市場に受け入れられ、収益の柱として成長したか」という観点で見ると、成功率はさらに低くなると考えられます。
多くの現場では、100の事業アイデアのうち、事業化の検討に進むのは10程度、その中で実際に市場にリリースされ、単独で黒字化を達成できるのは良くて1つか2つ、というのが共通認識ではないでしょうか。
社内だけで進める際に立ちはだかかる「3つの壁」
では、なぜこれほどまでに新規事業は難しいのでしょうか。特に、既存事業で成功している企業ほど、社内だけでプロジェクトを進めようとすると、特有の「壁」に直面しがちです。
1. ノウハウ・経験の壁:
新規事業開発には、市場リサーチ、ビジネスモデル設計、MVP(Minimum Viable Product: 顧客価値を検証するための最小限の製品)開発、アジャイルな仮説検証など、既存事業の運営とは全く異なるスキルセットと経験が必要です。これらのノウハウを持つ人材は、社内にはほとんどいないのが実情です。
2. リソース・組織の壁:
「新規事業担当」といっても、既存業務との兼任であったり、十分な予算や人員が割り当てられなかったりするケースは少なくありません。また、短期的な成果を求める既存事業部門からのプレッシャーや、部門間の連携不足といった組織の壁が、プロジェクトの推進を妨げます。
3. 客観性・マインドセットの壁:
自社の技術やサービスに愛着があるほど、「こうあるべきだ」「これは売れるはずだ」という思い込み(バイアス)に囚われやすくなります。顧客の本当のニーズを客観的に捉え、時には大胆な方向転換(ピボット)を決断することができず、プロジェクトが停滞・失敗してしまうのです。
2. 今、注目される「伴走支援」とは?従来のコンサルティングとの決定的な違い

これらの壁を乗り越えるために外部の専門家を活用するわけですが、ここで「従来のコンサルティング」と「伴走支援」の違いを明確に理解しておくことが重要です。
伴走支援の定義:「答え」ではなく「成功プロセス」を共に創る
従来のコンサルティングが、市場調査レポートや事業戦略といった「成果物(アウトプット)」を納品することを主たる目的とするのに対し、伴走支援は、クライアント企業のチームの一員のようにプロジェクトに深く参画し、戦略立案から実行、検証、改善までのプロセス全体を「共に」進めていくことを特徴とします。
| 比較軸 | 従来のコンサルティング | 新規事業 伴走支援 |
|---|---|---|
| 提供価値 | 調査レポート、戦略提案書などの「正解(とされる答え)」 | 事業を推進する「仕組み」と「ノウハウ」、実行支援 |
| 関与の仕方 | 第三者的な立場からのアドバイス、成果物の納品 | プロジェクトメンバーとして計画から実務まで一気通貫で参画 |
| ゴール | 契約で定められた成果物の納品 | 事業の成功、自社チームの育成、ノウハウの社内蓄積 |
| 関係性 | 「発注者」と「受注者」 | 共に汗をかく「パートナー」 |
つまり、魚を与えるのではなく、魚の釣り方を一緒に実践しながら教え、最終的には自社だけで魚を釣れるようになること(事業の自走化)を目指すのが、伴走支援の最大の価値と言えるでしょう。
陥りがちな失敗例:計画書は完璧、でも事業は動かない
綿密な市場調査に基づき、論理的で完璧な事業計画書を策定したにもかかわらず、プロジェクトが頓挫してしまうケースは後を絶ちません。その原因の多くは、計画の「実行」段階で生じる現場の課題や、顧客ニーズとの微妙なズレにあります。
計画が精緻であるほど、予期せぬ事態への対応が遅れ、結果として市場投入のタイミングを逃してしまうのです。このような失敗を防ぐには、計画を立てるだけでなく、実行プロセスに寄り添い、共に課題を解決するパートナーの存在が不可欠です。
伴走支援のメリット・デメリット
この点を踏まえ、伴走支援のメリットと、知っておくべきデメリットを整理します。
メリット:
●実践的なノウハウが社内に蓄積される: 共にプロジェクトを進める中で、担当メンバーのスキルが向上し、会社全体の事業創造力が強化されます。
●スピーディな意思決定と軌道修正が可能になる: チームの一員として動くため、市場の変化や検証結果に対して、迅速かつ柔軟に対応できます。
●客観的な視点を常に維持できる: 社内のしがらみやバイアスから解放された第三者の視点が入ることで、冷静な判断が可能になります。
●チームのモチベーションが向上する: 担当者が一人で悩みを抱え込むことがなくなり、専門家という仲間がいることで、心理的な負担が軽減され、挑戦への意欲が湧きます。
デメリットと対策:
●依存のリスク: パートナーに頼りきりになり、自社で考えることを放棄してしまう可能性があります。
○対策: 契約の初期段階で、「いつまでに」「どのような状態」を目指すのか(自走化のゴール)を明確に合意しておくことが重要です。
●コスト: 従来のコンサルティングと同様、安価ではありません。
○対策: 費用対効果を厳しく見極める必要があります。単なる実務代行ではなく、「ノウハウ移転」や「人材育成」といった無形の価値も考慮して投資判断を行いましょう。
●相性の問題: パートナーとの相性が悪いと、プロジェクトが円滑に進まない可能性があります。
○対策: 契約前に、実際にプロジェクトを担当するメンバーと面談し、スキルだけでなく、価値観やコミュニケーションのスタイルが自社の文化と合うかを慎重に見極めるべきです。
3. 【フェーズ別】新規事業における伴走支援の具体的な活用法

伴走支援は、新規事業のあらゆるフェーズで活用できます。ここでは代表的な4つのフェーズごとに、どのような支援が受けられるのかを解説します。
| フェーズ | 主な活動内容 | 伴走支援の活用例 |
|---|---|---|
| 1. アイデア創出・リサーチ | 市場調査、顧客ニーズ探索、技術シーズの評価、アイデアソン運営 | ・効果的なリサーチ手法の設計と実行支援 ・顧客インタビューの設計、同席、分析 ・社内アイデア創出ワークショップのファシリテーション |
| 2. 事業戦略・企画立案 | ビジネスモデル設計、事業計画策定、マネタイズ戦略立案 | ・実現可能性の高いビジネスモデルの壁打ち・共同設計 ・投資家や経営層を説得できる事業計画書の作成支援 ・KGI/KPI設計、ロードマップ策定 |
| 3. MVP開発・仮説検証 | プロトタイプ/MVPの要件定義・開発、顧客への実証実験、仮説検証サイクルの実行 | ・MVPの仕様策定支援、開発ベンダーとの連携 ・仮説検証(リーンスタートアップ)サイクルの導入・運営 ・ユーザーテストの結果分析と改善提案 |
| 4. 本格展開・グロース | マーケティング戦略、営業体制の構築、アライアンス、継続的なサービス改善 | ・初期顧客獲得のためのマーケティング・セールス施策の実行支援 ・事業成長に合わせた組織体制・採用計画の助言 ・アライアンス先との交渉同席 |
自社が今どのフェーズにいて、何に最も課題を感じているのかを明確にすることで、必要な支援を的確に得ることができます。
4. 【絶対失敗しない】信頼できる伴走支援パートナーを見極める5つの重要ポイント

では、数多く存在する支援会社の中から、本当に信頼でき、成果にコミットしてくれるパートナーをどう見つければ良いのでしょうか。絶対に外してはいけないと考える5つのポイントをお伝えします。
ポイント1:実績の「数」より「質」と「再現性」を見る
「支援実績300社以上!」といった数だけをアピールする会社には注意が必要です。本当に見るべきは、その質です。
●どのような業界で、どのような規模の事業を、どのフェーズから支援し、どのような成果(売上、顧客数、黒字化など)を出したのか。具体的な成功事例を複数確認しましょう。
●特に、自社と似たような業界や課題を持つ企業の支援実績があるかは重要な判断材料です。
●成功の要因を論理的に説明でき、そのノウハウが他のプロジェクトでも活かせるメソッド(方法論)として体系化されているかを確認しましょう。
ポイント2:担当者の「専門性」と「人間性」を確かめる
伴走支援は人が全てと言っても過言ではありません。契約前に、プロジェクトに中心的に関わる担当者本人と必ず面談してください。
●専門性: その担当者は、本当に新規事業の現場を経験してきたのか。机上の空論ではなく、実務レベルの知見やスキルを持っているか。過去の具体的な役割や貢献を深く質問してみましょう。
●人間性: あなたやあなたのチームメンバーが「この人と一緒に働きたい」と心から思えるか。高圧的でなく、真摯に話を聞き、同じ目線で議論できるパートナーか。この相性が、困難な局面を乗り越える際の推進力になります。
ポイント3:支援体制の「柔軟性」と「コミットメント」を問う
どこまで深く、柔軟にプロジェクトに関わってくれるのかは、会社によって大きく異なります。
●週1回の定例会だけという形式的な関与ではなく、日々のビジネスチャットツールでの相談や、緊急時の打ち合わせにスピーディに対応してくれるかを確認しましょう。
●「貴社のプロジェクトを成功させる」という強い意志、コミットメントを感じられるか。時には厳しい意見も、事業の成功のために率直に伝えてくれる誠実さがあるかを見極めてください。
ポイント4:契約形態と料金体系の「透明性」を確認する
料金体系は明確でなければなりません。
●「コンサルティング一式」のような曖昧な見積もりではなく、何に、どれくらいの工数がかかり、なぜその金額になるのか、詳細な内訳を提示してもらいましょう。
●プロジェクトの進捗に応じて契約内容を見直せるような、柔軟な契約形態(月額固定、レベニューシェアなど)が用意されているかも、パートナーの自信と誠実さを測るバロメーターになります。
ポイント5:ゴールと「成功の定義」を共有できるか
最後に、最も重要なのがこの点です。
●このプロジェクトを通じて、最終的に何を目指すのか。単に新商品をリリースすることがゴールなのか、それとも事業部として黒字化することなのか。あるいは、社内にイノベーション文化を醸成することなのか。
●この「成功の定義」をパートナーと徹底的にすり合わせ、共有できるか。ゴールがずれていると、どんなに優秀なパートナーでも成果には繋がりません。
5. FAQ(よくある質問)
Q1: 伴走支援の費用相場はどれくらいですか?
A1: 支援内容、期間、関与度合いによって大きく異なりますが、月額50万円〜200万円程度が一般的なレンジです。特定の業務(リサーチ、資料作成など)を切り出したプランや、成果報酬型の契約を用意している会社もあります。複数の会社から見積もりを取り、支援内容と照らし合わせて慎重に比較検討することをおすすめします。
Q2: どのくらいの期間、支援を依頼するものですか?
A2: プロジェクトのフェーズによりますが、3ヶ月から1年程度の契約でスタートするケースが多いです。特に、事業の仮説検証サイクルを回すフェーズでは、最低でも6ヶ月程度は見ておくと良いでしょう。重要なのは、期間の終わり(=自走化)を意識してプロジェクトを進めることです。
Q3: 支援を依頼する前に、社内で準備しておくべきことはありますか?
A3: 以下の3点を整理しておくと、パートナーとのコミュニケーションがスムーズになります。
1. 新規事業にかける想いやビジョン: なぜこの事業をやりたいのか。
2. 現状の課題: 何に困っていて、誰に、何を助けてほしいのか。
3. 社内の体制と覚悟: 誰が中心メンバーで、どの程度の予算や裁量権があるのか。
Q4: アイデアが全くないゼロの状態でも相談可能ですか?
A4: はい、もちろん可能です。むしろ、ゼロから共にアイデアを探索していくフェーズを得意とする伴走支援パートナーは数多く存在します。企業の強み(技術、顧客基盤など)や市場のトレンドを分析し、事業のシーズ(種)を見つけ出す段階から支援してくれます。
Q5: 伴走支援と人材育成(研修)の違いは何ですか?
A5: 研修が知識やスキルを「教える」インプット中心の場であるのに対し、伴走支援は実際のプロジェクトというOJT(On-the-Job Training)を通じて、実践的にノウハウを「体得」していくプロセスです。研修で学んだことを、伴走支援を通じて実務で活かし、定着させていく、という組み合わせも非常に効果的です。
6. まとめと実践に向けて
この記事では、新規事業開発における伴走支援について、その価値から具体的な活用法、信頼できるパートナーの選び方までを網羅的に解説してきました。不確実性の高い新規事業においては、社内のリソースだけで全てを完結させるのは困難です。客観的な視点と専門的なノウハウを持つ外部パートナーと連携することが、成功の確率を大きく高めます。
重要なのは、自社の課題を正確に把握し、その課題解決に最適なパートナーを慎重に選定することです。
「まずは自社の状況を客観的に整理したい」
「具体的な支援内容や事例について、もっと詳しく知りたい」
このようにお考えでしたら、ぜひ専門家にご相談ください。多くの支援会社では、契約を前提としない無料の相談会やセミナーを実施しています。
▼プロに無料で相談する
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
監修者プロフィール
中村 勇志 (Nakamura Yushi)
●役職: 経営コンサルタント
●所属企業: 株式会社船井総合研究所
●経歴:
大学卒業後、大手広告代理店にてオンラインとオフラインを融合させたプロモーションを経験し、新規顧客獲得で全社トップの実績を上げる。その後、株式会社船井総合研究所に中途入社。
現在は、AIとデータを活用した「業績アップコンサルタント」として活動。小売業のEC業績アップ案件をきっかけに、SEO対策、店舗連携、商品開発、在庫最適化、BtoB営業の仕組み化、自社ECのプラットフォーム構築まで、幅広いテーマで企業の成長を支援。その実績が評価され「2021年度 船井総研ベストコンサルティング賞 第3位」を受賞。アミューズメント、保険代理業、自動車販売業など、多岐にわたる業界で年間売上を110%~130%以上向上させた支援実績を多数持つ。
●読者へのメッセージ:
新規事業は、情熱だけでなく客観的なデータ活用と、顧客に価値を届けるための戦略的なプロモーションが成功の鍵を握ります。広告代理店で培った「顧客視点」と、船井総研で磨いた「データドリブンな経営改善」の両面から、皆様の新たな挑戦を全力でサポートいたします。どんな些細な悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。
________________________________________
監修者所属企業
株式会社船井総合研究所
船井総合研究所は、1970年に創業した日本最大級の経営コンサルティング会社です。「サステナグロースカンパニーをもっと。」というパーパスを掲げ、日本経済の根幹を成す中堅・中小企業の持続的成長を支援しています。
各業界に特化した専門コンサルタントを950名以上擁し(2024年4月時点)、現場に深く入り込む「月次支援」と、最新の成功事例を共有する「経営研究会」を両輪とした独自のスタイルで、クライアントの業績向上に貢献しています。その支援実績は国内トップクラスを誇り、東京証券取引所プライム市場にも上場しています。
●会社名: 株式会社船井総合研究所(Funai Soken Inc.)
●事業内容: 経営コンサルティング事業、DX支援事業、M&A支援事業 等
●設立: 1970年3月6日
●資本金: 30億円(2023年12月末時点)
●上場市場: 東京証券取引所 プライム市場
●東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 八重洲セントラルタワー35階
●大阪本社: 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10
●公式サイト: https://www.funaisoken.co.jp/
執筆: B-search