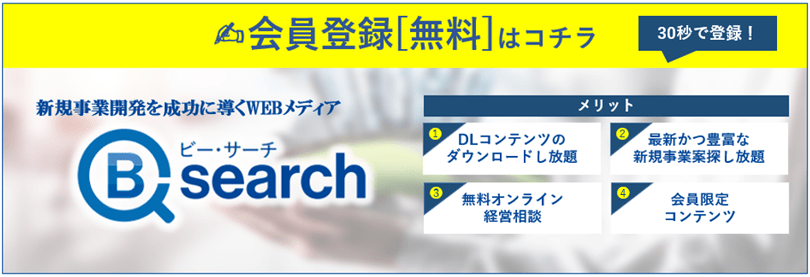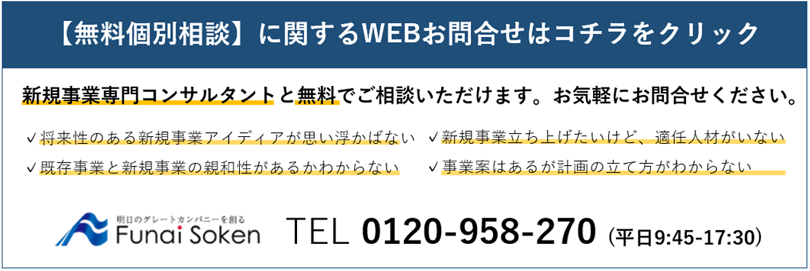「新しい事業のアイデアが浮かんだが、本当にニーズがあるのだろうか?」
「新規事業の立ち上げを任されたが、何から手をつければいいか分からない…」
「市場調査が重要だとは聞くけれど、具体的なやり方が分からず、時間だけが過ぎていく…」
新規事業の担当者であれば、一度はこのような悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。素晴らしいアイデアや技術も、市場のニーズと合致しなければ、事業を成功に導くことは困難です。その羅針盤となるのが「市場調査」ですが、いざ自社で行うとなると、その手法の多さや、どこまで調査すれば十分なのかという判断の難しさに、立ち止まってしまう方も少なくありません。
ご安心ください。この記事を読めば、その不安は解消されます。
本記事では、数多くの新規事業支援に携わってきたプロの視点から、新規事業における市場調査の全貌を、体系的かつ具体的に解説します。
この記事を読むことで、以下の内容が明確になります。
●新規事業における市場調査の本当の目的と重要性
●明日から実践できる、具体的な市場調査のステップと手法
●調査を成功に導き、失敗を避けるための実践的なポイント
●自社で実施すべきか、専門の調査会社に依頼すべきかの明確な判断基準
机上の空論ではありません。多くの企業で見られる成功事例や失敗事例を交えながら、自信を持って新規事業の第一歩を踏み出すためのノウハウをお伝えします。ぜひ最後までお付き合いください。
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
Table of Contents
なぜ新規事業の成功に市場調査が不可欠なのか?【よくある失敗事例】

「市場調査の重要性は分かっている」という方は多いでしょう。しかし、その本当の意味を深く理解することが、成功への第一歩です。
ここで、新規事業でよく見られる失敗事例を一つ紹介します。
ある企業で、画期的な業務効率化を目的とした新しいビジネスチャットツールの開発プロジェクトが立ち上がりました。経営陣も担当者も「こんなに素晴らしいサービスなのだから、絶対に売れるはずだ」と、その技術力とアイデアに絶対の自信を持っていました。社内は熱気に包まれ、市場調査も最低限で済ませ、すぐに開発へと突き進んでしまったのです。
結果はどうだったか。鳴り物入りでリリースしたサービスは、ほとんど使われませんでした。原因を究明するために改めて顧客にヒアリングすると、衝撃の事実が判明しました。「確かに便利そうだけど、今使っているツールで十分だし、乗り換える方が手間だ」「その機能、我々の業界ではあまり必要ないんだよね」。
この企業は、自分たちの「こうあるべきだ」という思い込みで、顧客を見ていたのです。顧客が本当に抱えている課題、業務上の慣習、そして変化に対する抵抗感――そういった「生々しい現実」を全く把握できていませんでした。多額の投資と多くの時間を費やしたこの事業は、残念ながら数年で撤退を余儀なくされました。
この事例が示すように、市場調査とは、単なる情報収集ではありません。それは、作り手側の「思い込み」を打ち砕き、事業の進むべき道を照らしてくれる、唯一の羅針盤なのです。
新規事業の成功確率を高め、失敗のリスクを最小限に抑える。そのために、市場調査は不可欠な活動と言えるでしょう。客観的なデータや顧客の声は、社内の意思決定を円滑にし、経営層を説得するための強力な武器にもなります。
新規事業における市場調査の全体像|成功への7ステップ

市場調査を闇雲に始めてはいけません。効果を最大化するためには、しっかりとしたプロセスを踏むことが重要です。ここでは、新規事業の市場調査における代表的な流れを7つのステップで解説します。
1. Step 1: 目的と課題の明確化
「何のために、何を明らかにしたいのか」を定義します。例えば、「この新規事業の参入可能性を判断したい」「ターゲットとすべき顧客層を特定したい」「最適な価格設定を知りたい」など、調査のゴールを具体的に設定します。
2. Step 2: 仮説の設定
目的を達成するための「仮の答え」を設定します。例えば、「30代の共働き世帯は、時短調理ができるこのサービスに月額3,000円を払うだろう」といった仮説です。この仮説が正しいかを検証することが、調査の主目的となります。
3. Step 3: 調査計画(リサーチプラン)の策定
誰に(調査対象)、何を(調査項目)、どのように(調査手法)、いつまでに(スケジュール)、いくらで(予算)調査するのかを具体的に計画します。
4. Step 4: 調査票・インタビュー項目の設計
アンケートの質問票や、インタビューで聞くべき項目リストを作成します。仮説を検証するために、バイアスのない適切な質問を設計することが求められます。
5. Step 5: 実査(情報収集)
計画に沿って、アンケートやインタビューなどの調査を実行します。デスクリサーチで公開情報を集めるのもこの段階です。
6. Step 6: データ集計・分析
収集したデータを集計し、グラフなどを用いて可視化します。その後、データから何が言えるのかを深く分析し、仮説が正しかったのか、新たな発見はなかったかなどを考察します。
7. Step 7: レポーティングと意思決定
分析結果を報告書(レポート)にまとめ、関係者間で共有します。このレポートをもとに、事業を推進するのか、撤退するのか、あるいは方向性を修正するのかといった、次のアクション(意思決定)に繋げます。
この一連のプロセスを丁寧に行うことが、市場調査の精度を高める上で非常に大切です。
【手法を徹底比較】新規事業の市場調査、具体的な方法一覧
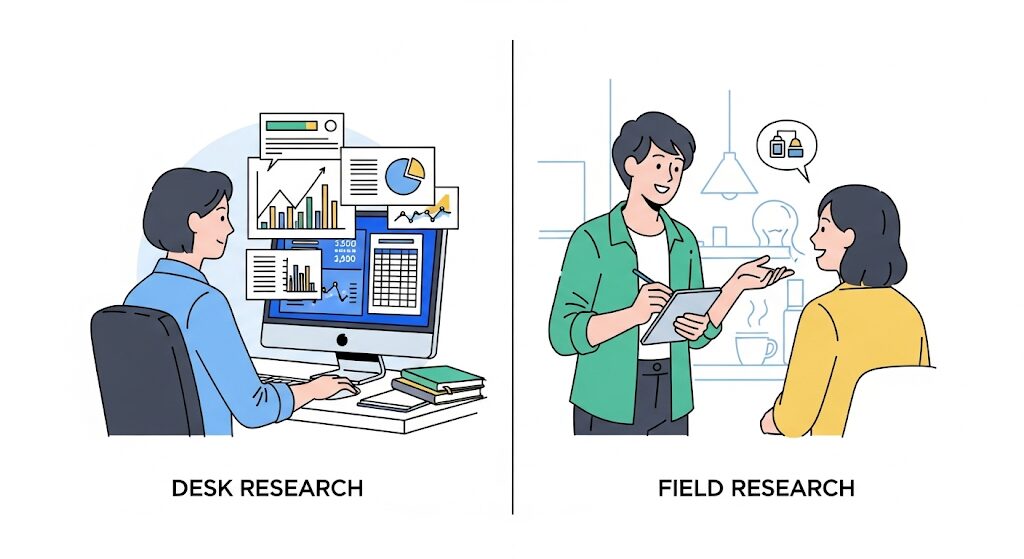
市場調査の手法は、大きく「デスクリサーチ(二次調査)」と「フィールドリサーチ(一次調査)」の2つに分けられます。それぞれに特徴があり、新規事業のフェーズや目的に応じて使い分けることが重要です。
まずはコストを抑えて始められる「デスクリサーチ(二次調査)」
デスクリサーチとは、既に公開されている統計データや調査レポート、文献、Webサイトなどを使って情報を収集する方法です。机(デスク)の上で完結することから、こう呼ばれます。比較的コストをかけずに、市場の全体像やマクロな動向を把握するのに適しています。
主なデスクリサーチの種類と情報源
●公的機関の統計データ:
信頼性が非常に高く、無料で利用できる情報が多いのが特徴です。市場規模や業界動向、消費者の動向などを把握するのに役立ちます。
○代表的な情報源:
■e-Stat(政府統計の総合窓口): 日本の人口、経済、社会に関するあらゆる統計データが集約されています。
■総務省統計局: 人口、労働力、家計などに関する詳細な統計を提供しています。
■経済産業省: 特定の業界動向や商業統計調査など、ビジネスに直結するデータが豊富です。
■中小企業庁: 中小企業白書などで、中小企業の動向や新規事業に関する調査結果が公開されています。
●民間の調査会社が公開しているレポート:
特定の業界やテーマに特化した調査レポートが公開されていることがあります。有料のものが多いですが、無料で概要版を公開しているケースもあります。
●業界団体の資料・論文:
各業界団体が発表している市場動向レポートや、大学・研究機関の論文も貴重な情報源です。
●新聞・ニュースサイト・専門メディア:
最新の市場トレンドや競合他社の動向を把握するのに役立ちます。キーワードを登録しておき、関連ニュースを日々チェックするのも有効です。
●競合他社のWebサイト・IR情報:
競合がどのようなサービスを展開し、どのような層をターゲットにしているのかを分析できます。上場企業であれば、IR情報から経営戦略や財務状況を把握することも可能です。
顧客の”生の声”を聞く「フィールドリサーチ(一次調査)」
フィールドリサーチとは、自社の調査目的のために、独自に企画して実施する調査です。デスクリサーチでは得られない、顧客の具体的なニーズや本音、行動といった「生の情報」を収集できるのが最大のメリットです。
このフィールドリサーチは、さらに「定量調査」と「定性調査」に分かれます。
●定量調査:数値で市場の実態を把握する
アンケート調査が代表的です。「はい/いいえ」や5段階評価などで回答してもらい、結果を「何パーセントの人が〜と考えている」といった数値(量)で把握します。市場規模の推定やニーズの有無、顧客層のボリュームを確認するのに適しています。
○手法の例:
■Webアンケート: 最も一般的な手法。調査会社のパネルを利用したり、SNS広告を使ったりして回答者を集めます。比較的低コストで多くのサンプルを集めやすいのがメリットです。
■会場調査(CLT): 会場に調査対象者を集め、製品を試用してもらってからアンケートに回答してもらう手法。実際の反応を見ながら調査できます。
●定性調査:背景にある「なぜ?」を深掘りする
数値では表せない、顧客の意見や感情、行動の背景にある動機などを深く理解するための調査です。なぜそのように感じるのか、どういった点に不満があるのかといった「質」的な情報を得られます。
○手法の例:
■デプスインタビュー: 調査対象者とインタビュアーが1対1で、30分~1時間程度、深く対話する手法。本音を引き出しやすく、新たなインサイト(発見)を得られる可能性が高いです。
■グループインタビュー: 複数の調査対象者(4~6名程度)を集めて座談会形式で行う手法。参加者同士の会話の中から、多様な意見やアイデアが生まれることがあります。
■行動観察調査(エスノグラフィ): 顧客が実際に製品やサービスを利用している現場を観察し、無意識の行動や隠れた課題を発見する手法です。
【事例】インタビューが生んだ事業ピボット
あるITスタートアップ企業では、当初は「多機能で高スペックなツール」の開発を目指していました。しかし、コンサルティングを導入し、ターゲット顧客候補へのデプスインタビューを実施したところ、意外な事実が判明しました。「高機能は使いこなせない。それよりも、たった一つでいいから、今の面倒な〇〇作業を自動化してくれるだけでいい」という声が多数聞かれたのです。
この”生の声”をもとに、事業計画を大幅に修正。機能を絞ったシンプルなツールに切り替えてリリースした結果、特定のニーズを持つ顧客に深く刺さり、事業は無事に軌道に乗りました。フィールドリサーチの価値を改めて示す事例です。
手法別メリット・デメリット・費用感の比較
| 調査手法 | 大別 | 主な目的 | メリット | デメリット | 費用感(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| デスクリサーチ | 二次調査 | 市場の全体像把握、マクロ動向の理解 | ・低コスト、短期間で実施可能 ・客観的なデータを得やすい |
・自社が知りたい情報がピンポイントで存在するとは限らない ・情報が古い可能性がある |
無料~数万円 |
| 定量調査(Webアンケート等) | 一次調査 | 市場規模の把握、仮説の量的検証 | ・多くの対象者からデータを集められる ・結果を数値で示せるため説得力が高い |
・「なぜそう思うか」という背景までは分かりにくい ・調査票の設計が結果を左右する |
10万円~100万円以上 |
| 定性調査(インタビュー等) | 一次調査 | 顧客ニーズの深掘り、インサイト発見 | ・消費者の本音や潜在ニーズを引き出せる ・新たなアイデアのヒントが得られる |
・対象者数が少ないため、結果の一般化は難しい ・インタビュアーのスキルに依存する部分が大きい |
30万円~200万円以上 |
失敗しない市場調査、成功確率を上げる5つのポイント

ここまで様々な手法を紹介してきましたが、ただ実施するだけでは意味がありません。ここでは、調査の質を高め、新規事業の成功に繋げるための5つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:調査の「目的」と「課題」をとことん明確にする
「とりあえず市場を調べてみよう」というスタートは、多くの場合、失敗に終わります。膨大な時間とコストをかけたのに、結局「で、何が分かったんだっけ?」という状態に陥ってしまうのです。
そうならないために、調査を始める前に、「この調査で何を明らかにし、その結果をどういう意思決定に使うのか」を、関係者全員で徹底的に議論し、言語化してください。
●曖昧な例: 新規サービスの市場性を知りたい。
●明確な例: 我々の新規フィットネスサービス(月額1万円想定)のメインターゲットは30代女性と仮定している。この層の潜在的な市場規模はどの程度か、また、彼女たちがサービスの対価として1万円を支払う意思があるかを検証し、事業化のGO/NO-GOを判断する。
目的が明確であれば、自ずと最適な調査手法や質問項目が決まってきます。
ポイント2:思い込みを捨て、「精度の高い仮説」を立てる
市場調査は、仮説を検証するプロセスです。そして、その質は、出発点となる「仮説の質」に大きく左右されます。
「きっとこうだろう」という希望的観測や思い込みではなく、既存のデータや顧客へのヒアリングなど、何かしらの根拠に基づいた「精度の高い仮説」を立てることが重要です。
例えば、「この新機能は絶対にウケるはずだ」と考えるのではなく、その根拠を明確にすることが求められます。「競合B社の類似機能のユーザー満足度が高い」というデータや、「既存顧客へのヒアリングで肯定的な意見が多かった」といった事実に基づき、仮説の解像度を上げていく意識が大切です。
ポイント3:調査対象者を「具体的に」設定する
「20代~40代の男女」のような、漠然とした対象者設定では有効なデータは得られません。得られる回答もぼやけてしまい、結局誰に向けた事業なのかが分からなくなります。
ペルソナ(具体的な顧客像)を設定し、そのペルソナに合致する人を調査対象に選ぶことが極めて重要です。
●例:在宅勤務者向けの椅子を開発する場合
○NG: 20~50代の会社員
○OK: 週に3日以上在宅勤務をしており、自宅に専用のワークスペースがなく、リビングの椅子で仕事をしている。現在の作業環境に腰痛などの不満を感じている30代の会社員。
対象者をシャープにすればするほど、得られる情報の解像度は高まり、事業のターゲットも明確になります。
ポイント4:自社に都合の悪い「不都合な真実」から目をそらさない
人は誰しも、自分の考えを肯定してくれる情報を集めてしまう傾向(確証バイアス)があります。しかし、新規事業においては、むしろ自社の仮説を否定するような情報(=不都合な真実)こそが価値ある情報です。
●「我々のサービスは必要ない」
●「価格が高すぎる」
●「競合の〇〇の方が魅力的だ」
こうしたネガティブな意見にこそ、事業を成功に導くヒントが隠されています。調査を行う際は、意識的に「この仮説を否定する情報はないか?」という視点を持ち、客観的なデータ収集と分析を心がけてください。
ポイント5:調査会社(コンサル)に任せるべきかの判断基準
「結局、自社でやるべきか、プロに依頼すべきか」という点は、多くの担当者が悩むポイントです。これは非常に重要な経営判断となります。以下に判断基準のポイントをまとめます。
| 観点 | 自社で実施するメリット | 調査会社に依頼するメリット |
|---|---|---|
| コスト | 費用を安く抑えられる可能性 | 費用はかかるが、費用対効果は高い |
| 時間・リソース | 社員の稼働が必要 | 社内リソースを本業に集中できる |
| 専門性・客観性 | ノウハウが蓄積される | 専門的な知見や手法を活用できる客観的な視点での分析が期待できる |
| 品質・信頼性 | 品質が担当者のスキルに依存 | 高品質で信頼性の高いデータが得られる(経営層への説明材料として有効) |
【こんな場合は調査会社への依頼を検討】
●社内に調査のノウハウやリソースが全くない場合
●数千万円以上の大きな投資判断が伴う新規事業の場合
●経営陣や他部署を説得するための、客観的で信頼性の高いデータが必要な場合
●調査の企画から分析、戦略立案まで一気通貫で支援してほしい場合
調査会社を選ぶ際は、費用だけで決めず、自社の業界への理解度や実績、担当者との相性などをしっかり見極めることが大切です。複数の会社から提案や見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 新規事業の市場調査には、どのくらいの費用がかかりますか?
A1. 調査の規模や手法によって大きく異なります。デスクリサーチのみであれば無料~数万円程度で可能ですが、数千人規模のWebアンケート調査や複数のデプスインタビューを実施する場合、数十万円~数百万円以上かかることもあります。まずは目的を明確にし、どの程度の精度が必要かを考え、予算を策定することが重要です。
Q2. 調査にはどのくらいの期間がかかりますか?
A2. こちらも内容によりますが、目安として、デスクリサーチなら1週間~2週間、Webアンケート調査なら調査票作成からレポートまで含めて1ヶ月~1.5ヶ月、デプスインタビューなら対象者のリクルーティングも含めて1.5ヶ月~2ヶ月程度を見込むとよいでしょう。調査計画の段階で、しっかりスケジュールを立てることが大切です。
Q3. BtoB(法人向け)事業の市場調査で気をつける点は何ですか?
A3. BtoBの場合、調査対象となる企業の担当者を見つけるのが難しい点が特徴です。また、購買の意思決定が組織で行われるため、「誰に(決済者、利用者など)」聞くかが非常に重要になります。業界のキーマンへのインタビューや、特定の業界に詳しい調査会社の活用が有効な場合があります。
Q4. 調査結果をどのように事業戦略に活かせばよいですか?
A4. 調査結果は、次の意思決定に繋げて初めて価値が生まれます。例えば、「STP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)」を行って狙うべき市場を特定したり、「4P分析(製品、価格、流通、販促)」を用いて具体的なマーケティング戦略を策定したりします。分析結果から得られたインサイトをもとに、事業計画の精度を高めていくことが求められます。
Q5. 社内に市場調査の重要性が理解されません。どうすればよいですか?
A5. まずは小規模でも良いので、デスクリサーチや数人への簡単なヒアリングから始め、客観的なデータを示すことから始めてみましょう。特に、今回紹介したような「市場調査を怠ったことによる失敗事例」や、逆に「調査によって成功した事例」を具体的に共有することで、重要性を認識してもらいやすくなります。この記事を参考に、市場調査の目的や効果を資料にまとめて提案するのも有効です。
まとめと実践に向けて
今回は、新規事業における市場調査の重要性から具体的な手法、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
●市場調査の目的は、思い込みを捨て、客観的な事実に基づいて意思決定すること。
●調査は「目的設定→仮説→計画→実行→分析→意思決定」のプロセスに沿って行う。
●手法は「デスクリサーチ」と「フィールドリサーチ」があり、目的で使い分ける。
●成功の鍵は「明確な目的」「精度の高い仮説」「具体的な対象者設定」「不都合な真実の直視」。
●自社で行うか専門家に依頼するかは、コスト、リソース、専門性などを考慮して慎重に判断する。
市場調査は、時に手間やコストがかかる活動です。しかし、それは単なる「費用」ではありません。不確実性の高い新規事業という航海において、失敗という座礁のリスクを減らし、成功という目的地へと導いてくれる「未来への投資」なのです。
「記事を読んで、市場調査の重要性は分かった。でも、自社だけでやるには不安が残る…」
「私たちの事業の場合、具体的にどんな調査から始めるべきか相談したい」
もしあなたがそうお考えなら、一度、専門家の力を頼ってみませんか?
数多くの新規事業を支援してきたプロのコンサルタントが、あなたの会社の状況に合わせた最適な市場調査のプランをご提案します。
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
監修者プロフィール
中村 勇志 (Nakamura Yushi)
●役職: 経営コンサルタント
●所属企業: 株式会社船井総合研究所
●経歴:
大学卒業後、大手広告代理店にてオンラインとオフラインを融合させたプロモーションを経験し、新規顧客獲得で全社トップの実績を上げる。その後、株式会社船井総合研究所に中途入社。
現在は、AIとデータを活用した「業績アップコンサルタント」として活動。小売業のEC業績アップ案件をきっかけに、SEO対策、店舗連携、商品開発、在庫最適化、BtoB営業の仕組み化、自社ECのプラットフォーム構築まで、幅広いテーマで企業の成長を支援。その実績が評価され「2021年度 船井総研ベストコンサルティング賞 第3位」を受賞。アミューズメント、保険代理業、自動車販売業など、多岐にわたる業界で年間売上を110%~130%以上向上させた支援実績を多数持つ。
●読者へのメッセージ:
新規事業は、情熱だけでなく客観的なデータ活用と、顧客に価値を届けるための戦略的なプロモーションが成功の鍵を握ります。広告代理店で培った「顧客視点」と、船井総研で磨いた「データドリブンな経営改善」の両面から、皆様の新たな挑戦を全力でサポートいたします。どんな些細な悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。
________________________________________
監修者所属企業
株式会社船井総合研究所
船井総合研究所は、1970年に創業した日本最大級の経営コンサルティング会社です。「サステナグロースカンパニーをもっと。」というパーパスを掲げ、日本経済の根幹を成す中堅・中小企業の持続的成長を支援しています。
各業界に特化した専門コンサルタントを950名以上擁し(2024年4月時点)、現場に深く入り込む「月次支援」と、最新の成功事例を共有する「経営研究会」を両輪とした独自のスタイルで、クライアントの業績向上に貢献しています。その支援実績は国内トップクラスを誇り、東京証券取引所プライム市場にも上場しています。
●会社名: 株式会社船井総合研究所(Funai Soken Inc.)
●事業内容: 経営コンサルティング事業、DX支援事業、M&A支援事業 等
●設立: 1970年3月6日
●資本金: 30億円(2023年12月末時点)
●上場市場: 東京証券取引所 プライム市場
●東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 八重洲セントラルタワー35階
●大阪本社: 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10
●公式サイト: https://www.funaisoken.co.jp/
執筆: B-search