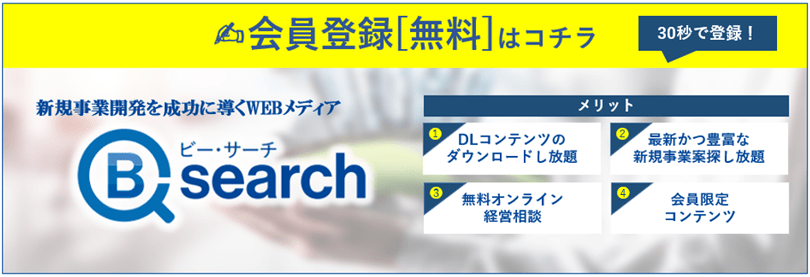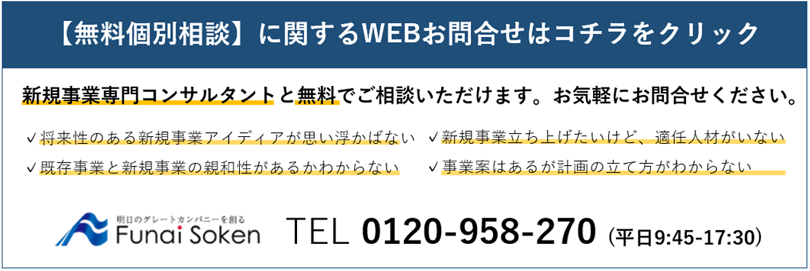「自社の持続的成長のために、新規事業を立ち上げたい」
「SDGsや地域貢献の観点から、農業分野に注目している」
「しかし、農業は未経験。何から手をつければいいのか、本当に事業として成り立つのか、見当もつかない…」
企業の経営企画や新規事業開発に携わる中で、このようなお悩みを抱えてはいないでしょうか。
近年、IT、建設、小売など、様々な業界の企業から農業分野への新規参入に関するご相談が非常に増えています。確かに、農業は「儲からない」「大変」といったイメージが根強く、異業種からの参入には特有のハードルが存在します。
しかし、それは裏を返せば、正しい知識と戦略さえあれば、大きなビジネスチャンスが眠っているということでもあります。
この記事では、多くの新規事業支援に携わってきた専門家の視点から、以下の内容を徹底的に、そして分かりやすく解説します。
●なぜ今、農業への新規参入がビジネスチャンスなのか
●新規参入企業が陥りがちな、典型的な失敗パターンとその対策
●異業種から参入し、成功するための具体的な7つのステップ
●活用すべき国や自治体の手厚い支援制度・補助金
●事業を成功に導く、信頼できる相談相手の見極め方
この記事を最後までお読みいただければ、農業への新規参入に関する漠然とした不安が解消され、事業化に向けた明確なロードマップと、次にとるべき具体的なアクションが見えてくるはずです。ぜひ、貴社の未来を切り拓くヒントを掴んでください。
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
Table of Contents
1. なぜ今、異業種の農業参入がビジネスチャンスなのか?
「農業は衰退産業」そんなイメージがあるかもしれません。しかし、見方を変えれば、大きな変革期にある今だからこそ、新規参入のチャンスが広がっているのです。
日本の農業が抱える課題と、そこに眠る「機会」
日本の農業は、ご存知の通り「農業就業人口の減少と高齢化」という大きな課題に直面しています。農林水産省のデータによれば、2023年の農業就業人口は116.3万人と、この20年で半分以下に減少しました。(出典:農林水産省「令和5年農業構造動態調査結果」)
これは深刻な状況ですが、ビジネスの視点で見ると、既存のやり方では立ち行かなくなった「非効率」な部分が多く残されていることを意味します。ここに、異業種が持つ経営ノウハウや技術、資本を投入することで、生産性を劇的に向上させ、新たな価値を創出する大きな可能性があります。
市場の動向:スマート農業と6次産業化という追い風

近年、農業分野でのビジネスチャンスを大きく広げているのが、以下の2つのキーワードです。
●スマート農業/農業DX: ドローンによる農薬散布、センサー技術を活用した水管理、AIによる生育予測など、ICT技術で農業の省力化・高品質化を実現する取り組みです。これにより、これまで経験と勘に頼りがちだった農作業をデータに基づいて管理・最適化できるようになり、農業経験の少ない企業でも参入しやすくなっています。
●6次産業化: 農産物を生産するだけでなく、自社で加工(2次産業)し、流通・販売(3次産業)まで一体的に行う経営形態です。「1次×2次×3次」で6次産業と呼ばれます。例えば、自社で育てたトマトでジュースやソースを開発し、自社のECサイトや直売所で販売するといった形です。これにより、付加価値が向上し、収益の安定化と拡大が期待できます。
これらの動きは、単なる生産者にとどまらない、新しい「農業ビジネス」の形を創り出す原動力となっています。
国も後押し!企業参入を促進する支援と規制緩和
担い手不足に悩む国や自治体も、企業の農業参入を積極的に後押ししています。
特に大きな変化が、農地法の改正です。以前は農業生産法人でなければ農地の所有が認められませんでしたが、リース(賃借)であれば一般の株式会社でも参入しやすくなるよう、要件が緩和されてきました。
さらに、後述する各種補助金や支援制度も充実しており、初期投資の負担を軽減し、事業を軌道に乗せるためのサポート体制が整えられています。
2. 【よくある失敗パターンから学ぶ】新規事業で農業に参入する際の5つのリアルな課題と対策
大きな可能性がある一方で、安易な参入が失敗に繋がるケースも少なくありません。ここでは、新規参入企業が陥りがちな典型的なパターンと、そこから見えてくるリアルな課題について解説します。
陥りがちな「理想先行」の失敗パターン
あるIT企業のケースでは、「最新の植物工場を導入すれば、未経験でも計画通りに高品質な野菜が安定生産できるはずだ」という計画で、都心からほど近い場所に大規模な施設を建設しました。
しかし、実際に稼働させてみると、計画通りに収量が伸びません。原因を調査したところ、地域の気候特性(特に夏場の高温多湿)に対する空調設備のスペックが不十分で、病気が発生しやすい環境になっていたことが判明しました。
当時の担当者からは、「データと技術さえあれば乗り越えられると考えていました。しかし、農業はそんなに単純ではなかった。太陽や土、地域の気候といった、コントロールできない自然が相手だということを痛感しました。もっと現場の農家さんや、地域のことをよく知る専門家の声に耳を傾けるべきだった」という声が聞かれました。
このケースのように、異業種からの参入で最も陥りやすいのが、「自社の技術やノウハウがあれば、農業の特殊性を乗り越えられる」という思い込みです。農業は自然を相手にする産業であり、地域ごとの環境や文化が深く関わっていることを忘れてはいけません。
参入障壁となる5つのリアルな課題と具体的な対策
この失敗パターンも踏まえ、新規参入企業が直面しがちな5つの課題と、その対策を表にまとめました。
| 課題 | 内容 | 具体的な対策 |
|---|---|---|
| 1. 農地の確保 | 「良い農地」は情報が出回りにくい。農地法などの法規制が複雑で、手続きが煩雑。 | ・自治体の農政課、農業委員会、全国農地ナビで情報収集。・地域のキーマン(JA、土地改良区、ベテラン農家など)との関係構築。・農地法に詳しい行政書士やコンサルタントに相談。 |
| 2. 資金調達 | 施設や機械の導入に多額の初期投資が必要。収益化までに時間がかかり、運転資金の確保が重要。 | ・日本政策金融公庫の融資制度を活用。・国や自治体の補助金・助成金を徹底的にリサーチし、事業計画に盛り込む。・綿密な収支計画を作成し、複数の金融機関に相談。 |
| 3. 技術・ノウハウ | 作物の栽培技術は一朝一夕には身につかない。安定生産には専門的な知識と経験が必要。 | ・農業大学校や民間の研修機関で学ぶ。・経験豊富な農業者を技術顧問として採用・提携する。・まずは小規模で試験栽培(PoC)から始める。・スマート農業技術を導入し、技術習得をサポートする。 |
| 4. 人材の確保・育成 | 農業現場で働く人材の確保が難しい。特に、栽培技術と経営感覚を併せ持つリーダー人材は希少。 | ・地域の農業法人やハローワークと連携。・移住支援制度などを活用し、都市部からの人材を呼び込む。・自社内でのキャリアパスや魅力的な労働環境(休日確保、福利厚生など)を整備する。 |
| 5. 販路の開拓 | 「作っても売れない」問題。市場や農協出荷だけでは価格が安定しにくい。独自の販路開拓が不可欠。 | ・事業計画の段階で、ターゲット消費者と販売戦略を明確にする。・地域の直売所、飲食店、ホテルなどへの直接販売。・ECサイトやSNSを活用したオンライン販売。・加工品開発(6次産業化)による出口戦略の多様化。 |
3. 農業での新規事業、成功への7ステップ【完全ガイド】

では、具体的にどのようなステップで進めれば、失敗のリスクを減らし、成功の可能性を高めることができるのでしょうか。ここでは、事業化に向けた7つのステップを解説します。
Step 1: 事業目的とビジョンの明確化「なぜ、自社が農業をやるのか?」
まず最初に、「なぜ農業なのか?」を徹底的に突き詰めます。「儲かりそうだから」「SDGsに貢献できそうだから」といった漠然とした理由だけでは、前述のような困難に直面した際に事業が頓挫してしまいます。自社の既存事業とのシナジーは何か、経営理念とどう結びつくのか、この「軸」が今後のあらゆる意思決定の拠り所となります。
Step 2: 徹底的な情報収集と市場・地域分析
次に、机上調査と現地調査を徹底的に行います。どの作物に需要があるかといった市場分析、参入候補地の気候や物流網、自治体の支援制度などを分析する地域分析が重要です。特に、実際に現地を訪れ、自分の目で見て、地域の人と話をすることが欠かせません。
Step 3: 収益の柱を作る事業モデルの検討
誰に、何を、どのように提供して収益を上げるのかを具体化します。生産に特化するのか、加工・販売まで行う6次産業化を目指すのか、または観光農園のようなサービス提供型か。自社の強みが活かせるモデルを考えましょう。
Step 4: 精度が命!事業計画書の作成
ここまでの内容を、具体的な数値目標に落とし込んだ事業計画書を作成します。生産計画、人員計画、販売計画、そして資金計画や収支計画などを盛り込みます。特に収支計画は、リスクも考慮した、現実的なシナリオを複数用意することが重要です。
Step 5: 農地の確保と法人設立の手続き
事業計画が固まったら、具体的なアクションに移ります。事業形態に合った法人を設立し、農業委員会等を通じて農地の賃貸借契約を進めます。農地法の許可申請が必要になるため、行政書士などの専門家と連携して進めるとスムーズです。
Step 6: 農業技術の習得と人材育成・確保
農業は「人」が資本です。地域の農業大学校や先進農家での研修などを通じて、従業員が実践的な技術を学ぶ機会を設けます。また、地域のハローワークや専門の求人サイトを活用し、働きがいのある環境を整備することで、良い人材を確保・定着させます。
Step 7: 「作って終わり」にしない販路開拓とマーケティング戦略
どんなに良い作物を作っても、売れなければ事業は成り立ちません。栽培と並行して、あるいはそれ以前から販路開拓を進めます。自社の農産物のこだわりを伝えるブランディング、ECサイトや直接販売など複数のチャネル開拓、SNSでの情報発信などを通じて、ファンを育てていく戦略が求められます。
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
4. 【ケーススタディ】異業種からの農業参入成功事例3選

| 参入企業 | 既存事業 | 農業事業モデル | 成功のポイント |
|---|---|---|---|
| A社 | IT・Webサービス | スマート農業による高付加価値野菜生産 自社開発の環境制御システムを導入した植物工場で、高品質なハーブや葉物野菜を生産。高級レストランやスーパーに販売。 | ・自社の技術力を活かし、生産工程をデータ化・最適化。・天候に左右されない安定供給体制を構築し、BtoB取引での信頼を獲得。・栽培データをサービスとして他の農業法人に提供し、新たな収益源を確保。 |
| B社 | 建設業 | 遊休地の活用と障がい者雇用 自社が保有する建設残土の仮置き場などを農地として再生。地域の福祉施設と連携し、障がいを持つ人々を雇用してキノコや野菜を栽培。 | ・既存アセット(土地・重機)を有効活用し、初期投資を抑制。・「農業 × 福祉(農福連携)」による社会貢献性が高く評価され、企業のイメージ向上と人材採用に繋がる。・自治体や地元企業が応援購入してくれるなど、地域を巻き込んだ販路を開拓。 |
| C社 | 食品小売業 | 観光農園による6次産業化 自社店舗のバックヤードに、いちご狩りができる観光農園を開設。収穫したてのいちごを使ったスイーツを開発し、併設のカフェや店舗で販売。 | ・既存の顧客基盤を活用し、集客コストを抑える。・「収穫体験」というコト消費を提供し、顧客満足度とリピート率を向上。・生産から加工、販売までを一気通貫で行うことで高い収益率を実現。 |
これらの事例に共通するのは、自社の強みを活かし、明確な戦略を持って参入している点です。
5. 【2025年版】活用しないと損!国や自治体の主要な支援制度・補助金
新規事業、特に農業のように初期投資がかかる分野では、公的な支援制度の活用が成功の鍵を握ります。すべてを網羅することはできませんが、代表的なものを紹介します。
代表的な補助金・支援制度
| 制度名 | 概要 | 対象者(一例) |
|---|---|---|
| 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 収益力向上や担い手確保のために、農業用機械・施設の導入、リースなどを総合的に支援する。 | 認定農業者、地域計画に位置づけられた者 等 |
| 農地利用効率化等支援交付金 | 担い手への農地集積・集約化を支援する。 | 担い手、農地中間管理機構 等 |
| スマート農業技術導入支援 | AI、IoT、ドローン等のスマート農業技術の導入を支援する。 | 農業者、農業法人 等 |
| 6次産業化関連の補助金 | 新商品の開発や販路開拓、加工施設の整備などを支援する。 | 農林漁業者、中小企業者 等 |
※これらの制度は年度によって内容が変更されたり、公募期間が定められていたりします。必ず公式サイトや担当窓口で最新の情報を確認してください。
まずは気軽に相談できる専門窓口一覧
何から調べればいいか分からない、という場合は、まず以下の専門窓口に相談してみるのが良いでしょう。無料で相談に乗ってくれるところがほとんどです。
●全国新規就農相談センター: 全国レベルでの就農・参入に関する情報提供や相談対応を行っています。
●各都道府県の就農支援センター: 地域に特化した情報(空き農地、地域の担い手など)を提供してくれます。
●自治体(市区町村)の農政課・農業委員会: 農地に関する手続きや、地域独自の支援制度について相談できます。
●農地中間管理機構(農地バンク): 農地を借りたい企業と、貸したい農家をマッチングしてくれます。
6. 失敗しないためのパートナー(コンサルタント)の選び方

情報収集や計画作成に行き詰まった際、外部の専門家の活用は非常に有効な選択肢です。良いパートナーを見つけるためのポイントを3つご紹介します。
「良い相談相手」を見極める3つのポイント
1.実績の「具体性」: 「農業参入を支援しました」だけでなく、「どんな業種の企業を、どの地域で、どんな事業モデルで、どんな成果(売上、課題解決)に導いたか」を具体的に語れるかを確認しましょう。
2.「現場」への理解度: 机上の空論ではなく、農業の現場(土、気候、地域の人間関係など)の重要性を理解し、それに基づいた提案ができるかを見極めます。
3.「伴走」の姿勢: 一方的に指導するのではなく、企業の担当者と一緒になって悩み、汗をかき、事業を育ててくれる姿勢があるか。良いパートナーを見つけるためには、「なぜ農業なのか」という事業の根幹に関わるビジョンを共有できるかどうかが重要です。
7. FAQ(よくある質問)
Q1: 農業経験が全くなくても、異業種から参入できますか?
A1: はい、可能です。実際にITや建設など多くの異業種が参入し成功しています。成功の鍵は、自社の強みを活かしつつ、農業の専門家(技術顧問や地域のベテラン農家など)としっかり連携することです。また、農業大学校や各種研修制度を活用して、自社内に技術を持つ人材を育成することも重要です。
Q2: 農業への新規参入には、初期費用はどのくらいかかりますか?
A2: 事業の規模や内容(露地栽培か施設栽培か、など)によって大きく異なります。小規模な露地栽培なら数百万円から可能な場合もありますが、大規模な施設園芸や植物工場となると数千万円~数億円規模の投資が必要になることもあります。事業計画の段階で、補助金の活用も視野に入れながら、綿密な資金計画を立てることが不可欠です。
Q3: 農地はどのように探せばいいですか?
A3: まずは参入を検討している地域の自治体(農政課や農業委員会)や、各都道府県にある「農地中間管理機構(農地バンク)」に相談するのが第一歩です。これらの機関が、農地を貸したい農家と借りたい企業のマッチングを行っています。Webサイト「全国農地ナビ」で情報を検索することも可能です。
Q4: 収益化できるまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
A4: これも事業モデルや栽培する作物によりますが、一般的に投資回収には時間がかかるビジネスです。初年度から黒字化するのは難しく、3年~5年程度の中長期的なスパンで収支計画を立てるのが現実的です。特に果樹などは、植え付けから収穫まで数年かかる場合もあります。
Q5: 注目されている「6次産業化」に興味がありますが、何から始めればいいですか?
A5: まずは自社で生産する(あるいは計画している)農産物の特性を活かせる加工品は何か、市場にニーズはあるかを調査することから始めます。例えば、規格外の野菜を活用したカット野菜やスープ、果物を使ったジャムやジュースなどです。保健所の許可が必要な場合も多いため、事業計画の段階で関連法規や必要な施設・設備について確認しておくことが重要です。
まとめ:次の一歩を踏み出すために
この記事では、異業種から農業へ新規参入するためのポイントを、網羅的に解説してきました。
●ビジネスチャンス: 農業は課題が多いからこそ、異業種のノウハウや技術で新たな価値を創出する大きなチャンスがある。
●リアルな課題: 農地、資金、技術、人材、販路という5つの壁を認識し、事前に対策を講じることが重要。
●成功への道筋: 明確なビジョンを持ち、7つのステップに沿って着実に事業計画を進める。
●支援の活用: 国や自治体の補助金、専門の相談窓口を最大限に活用し、リスクを軽減する。
●パートナーシップ: 自社だけで抱え込まず、地域の専門家や信頼できるコンサルタントと連携する。
農業への新規参入は、決して簡単な道のりではありません。しかし、日本の「食」を支え、地域を活性化させ、企業の持続的な成長にも繋がる、非常にやりがいのある事業です。
「記事を読んで、やるべきことは分かった。でも、自社だけで進めるのはやはり不安だ…」
「自社に合った事業モデルや、活用できる補助金について、もっと具体的に相談したい」
そう感じられたなら、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
▼プロに無料で相談する
貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。
>>船井総研の無料経営相談はこちら
監修者プロフィール
中村 勇志 (Nakamura Yushi)
●役職: 経営コンサルタント
●所属企業: 株式会社船井総合研究所
●経歴:
大学卒業後、大手広告代理店にてオンラインとオフラインを融合させたプロモーションを経験し、新規顧客獲得で全社トップの実績を上げる。その後、株式会社船井総合研究所に中途入社。
現在は、AIとデータを活用した「業績アップコンサルタント」として活動。小売業のEC業績アップ案件をきっかけに、SEO対策、店舗連携、商品開発、在庫最適化、BtoB営業の仕組み化、自社ECのプラットフォーム構築まで、幅広いテーマで企業の成長を支援。その実績が評価され「2021年度 船井総研ベストコンサルティング賞 第3位」を受賞。アミューズメント、保険代理業、自動車販売業など、多岐にわたる業界で年間売上を110%~130%以上向上させた支援実績を多数持つ。
●読者へのメッセージ:
新規事業は、情熱だけでなく客観的なデータ活用と、顧客に価値を届けるための戦略的なプロモーションが成功の鍵を握ります。広告代理店で培った「顧客視点」と、船井総研で磨いた「データドリブンな経営改善」の両面から、皆様の新たな挑戦を全力でサポートいたします。どんな些細な悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。
監修者所属企業
株式会社船井総合研究所
船井総合研究所は、1970年に創業した日本最大級の経営コンサルティング会社です。「サステナグロースカンパニーをもっと。」というパーパスを掲げ、日本経済の根幹を成す中堅・中小企業の持続的成長を支援しています。
各業界に特化した専門コンサルタントを950名以上擁し(2024年4月時点)、現場に深く入り込む「月次支援」と、最新の成功事例を共有する「経営研究会」を両輪とした独自のスタイルで、クライアントの業績向上に貢献しています。その支援実績は国内トップクラスを誇り、東京証券取引所プライム市場にも上場しています。
●会社名: 株式会社船井総合研究所(Funai Soken Inc.)
●事業内容: 経営コンサルティング事業、DX支援事業、M&A支援事業 等
●設立: 1970年3月6日
●資本金: 30億円(2023年12月末時点)
●上場市場: 東京証券取引所 プライム市場
●東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 八重洲セントラルタワー35階
●大阪本社: 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10
●公式サイト: https://www.funaisoken.co.jp/
執筆: B-search