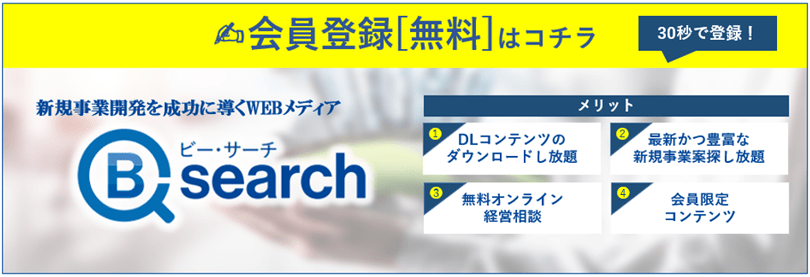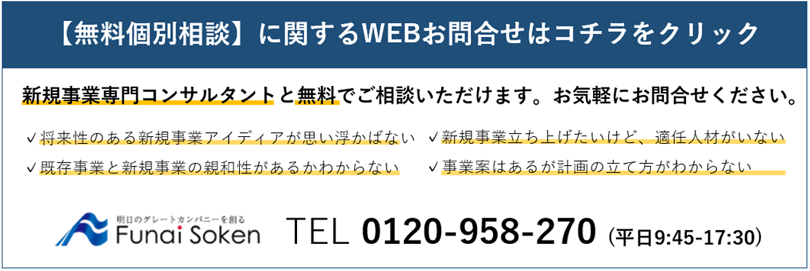新規事業開発のコンサルティングをしているとよく聞かれる質問として、組織や人員面でのご質問があります。有望な事業案を設計したとしても、組織としてそれを推進することができなければ事業は前に進みません。本コラムでは、新規事業開発を推進する人や組織について、実際の推進現場での知見を基にポイントをお伝えさせて頂きます。
Table of Contents
1.誰が推進する?
いきなり定性的な話になってしまいますが、やはり一番のポイントとしては、推進にあたって情熱を持っている方が推進することが最も大切だと考えております。会社規模によってはこれが経営者であることもありますし、社内起案の事業案であれば起案者であるケースもあります。
新規事業を推進していくときには不確実性も高いですし、既存事業とは比較にならないような広範な知識やスキルが求められます。しかし、それらを一人の方が全部自分でカバーする必要はありません。チームで対応することがほとんどです。しかし、各担当者や組織を束ねて「前に進める」ような推進力が、推進者には求められます。
情緒的な表現にはなってしまいますが、困難な状況を打破して「前に進める」情熱を持った推進者というのが、様々な現場を見させて頂いた上で、最も重要なポイントだと考えています。典型的な失敗例が、既存事業での非エース人材を充ててしまうケースで、「ヒマそうだから任せる」で成功するケースはかなり稀だと考えています。
2.組織はどうバックアップする?
では、(特に推進者が経営者でない場合)推進者に任せていて上手くいくかというと、それだけでは不十分だと考えています。特に組織としてバックアップすべきは、適切な経営資源を推進者に振り分けるとともに、推進者を心理的にバックアップしてあげることだと考えています。
当然、経営資源(お金以外に、各社内専門家のアサインや、事業で用いるモノやネットワークへのアクセス等)を推進者に振り分けてあげないと事業は進めません。そのため、こまめなコミュニケーションを取って推進者が今求めているものが何かを拾い上げて、振り分けてあげることが必要です。
一方で、推進者は既存事業から切り離され、短期的な成果を上げられないことへの焦燥感や、思わぬ障壁が現れたことによる目標との乖離のように、新規事業特有の不安にかられます。経営層として出来る具体的なこととして、例えば社内外への発表・発信の中で「この事業に懸けている」ことを明確にかつ繰り返しアピールすることが挙げられます。また、どうしても評価制度は既存事業をベースに作られていることが多いので、推進者が新規事業の担当になったことで不利になることが無いよう手配してあげることも重要だと思います。
新規事業開発には、技術・開発、マーケティング、営業、議事・法務など幅広い専門性が同時に必要とされます。リーダーを中心に、必要な専門家を揃えるためにも、社内横断・外部を含めたクロスファンクショナルなチーム編成がポイントです。
3.いつ組織化する?
新規事業も、いずれは軌道に乗ればその会社の「既存事業」になります。どこかのタイミングでは兼任者を専属化させたり、プロジェクトチームや経営トップが直接差配する体制から組織化する必要があります。一方で、組織とするには現実的に人が足りなかったり、リスクを伴う側面もあります。では、どのタイミングでどのような組織とするのが適切でしょうか?
もちろんこの質問に統一の答えがあるわけではありませんが、ある程度の目安を設定することが出きます。また事業計画時に、これらの事業フェーズ別の組織のあり方についてもある程度規定しておくことが望ましいと考えています。
事業化(案出し~検証、事業計画策定)までのフェーズでは、推進者以外はプロジェクトチームのような形で兼任者が集められるケースが一般的です。推進者についても兼任であるケースも多くありますし、新規事業推進部や経営企画室といった新規事業推進のための部署に異動となって推進するケースもあります。
推進者も兼任で検討が進むケースでも、ある程度事業の推進について経営判断がなされた後、事業推進のフェーズで専任化するケースがほとんどですが、スモールスタートで始められるような事業であれば兼任のまま事業立ち上げがなされるケースもあります。
ここまでの段階では、一時的に増加する人員ニーズと、採用・教育のリードタイムの乖離が発生して工数が不足することが一般的です。一方で社内の方も計画・推進における知見があるわけではない会社が多いのが実態です。したがってこのフェーズでは人員のアウトソーシングが行われるケースも多いです。私たちのようなコンサルティング会社もそうですが、例えば社内の法務・財務部署が既存事業を対象とした人員しかいないために、そうした知見をアウトソーシングするケースもよく見られます。
その後は、事業がある程度軌道に乗ってきた、または拡大させるフェーズに移行する段階で、正式な組織となるケースが一般的です。この段階になると、業務量も顧客の増加に従って増えてくるだけでなく、どのような業務が内部で必要で、それぞれのゴールやKPIが何で、どのような人材が必要かがある程度見えてきます。事前に撤退基準を設定している場合には、そのタイミングをクリアした段階で、同様に組織化するというケースもあります。
いかがでしたでしょうか?今回は、新規事業開発における人や組織について取り上げました。船井総研では、新規事業開発を行う企業様向けに、事業性評価や事業計画策定、立ち上げ伴走のご支援をさせて頂いております。貴社にて新規事業を検討されるにあたって、もしお困りごとや行き詰まりなどございましたら、ご相談だけでもぜひ一度お問い合わせ頂ければ、弊社コンサルタントが対応させて頂きます。
執筆: B-search